初出場を果たした聖隷クリストファー高校の校歌に盛り込まれた、美しい讃美歌の一節がSNSで大きな話題となっています。
特に心を打ったのは、冒頭のこの部分。
かみのひかりは 世のこみちの
くらきすみにも てりかがやく。
かみをたたえて なすつとめに
たかきひくきの へだてあらじ。
この歌詞は、「神の光(=神の愛や真理)は、地位や環境に関係なくすべての人を平等に照らす」という意味を持ちます。
暗く見通しの悪い場所にも光は届き、努力するすべての人を包み込む。そんな普遍的なメッセージが込められています。
SNSでの反応
SNSでは聖隷クリストファー高校 校歌で反響が多くあります。
聖隷クリストファー高校の校歌、もろ讃美歌そのもので笑った😊
メロディに歌詞を変えた校歌かと思ったら・・
甲子園に讃美歌流れるのいいじゃん!
調べたら「クリストファー」って"キリストを背負う人”って意味なんだってさ!#甲子園高校野球— クロワン (@uyiCC34FSVpc07w) August 9, 2025
かみのひかりは世のこみちの♪
聖隷クリストファーが甲子園初勝利。高校野球の“聖地”に初めて勝利の校歌「讃美歌393番」が流れた。
ユニークな校歌には、上宮の浄土宗宗歌「月影」がある。法然の作詞で、和歌なので短い。
36年前の甲子園アルプス席で、ワイは主将の元木大介の父・稔さんの隣で聴いた。 pic.twitter.com/qLbemCXGa3— 社会人野球のミカタ📰 (@shakaijin_base) August 9, 2025
聖隷クリストファー高校の校歌の作詞家の名前ながっ! ニコラウス・ルードヴィッヒ・フォン・ ツィンツェンドルフって……
— イチシキ太郎_タロスティア👂6/30シチュボ新作up (@midoriitisiki) October 25, 2013
聖隷クリストファー高校は、静岡県大会を勝ち抜き、念願の初出場を果たしました。
初戦では、春夏通じて通じて初出場の聖隷クリストファー(静岡)が、5―1で明秀日立(茨城)に勝利しました。
「光はどこにでも届く」という歌詞の通り、彼らの戦いぶりは甲子園のスタンドはもちろん、テレビの前の多くの人々にもまっすぐ届いたようです。
校歌誕生の背景
聖隷クリストファー高校の校歌は、キリスト教精神を基盤とする同校の理念を色濃く反映しています。
歌詞の中にある「高き低きのへだてあらじ」という表現は、聖書の教えにある「神の前に人は皆等しい」という思想をもとに作られたもの。
創立当初から「医療・福祉・教育を通じて社会に奉仕する人材を育てる」ことを使命とし、その理念を音楽で表現するために作られました。
学校名の由来
「聖隷」はキリスト教の奉仕精神を表す言葉で、「聖なる使命を持って人を助ける」という意味があります。
「クリストファー」はギリシャ語で「キリストを運ぶ者」を意味し、世界的に広く使われてきた名前です。
つまり、学校名全体で「キリストの愛をもって人々を導き、支える存在」を象徴しています。
この由来を知ると、甲子園で響いた校歌の一節が、単なる美しい言葉ではなく、学校全体の精神を映し出したものだとわかります。


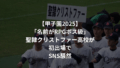
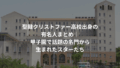
コメント